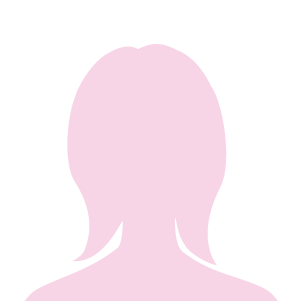ダイエットを始めて順調に体重が減っていたのに、ある日を境に体重が変わらなくなってしまった…
いわゆる「停滞期」と呼ばれる時期です。
この記事では停滞期を引き起こす原因と解決方法について、5つのタイプ別に紹介していきます。
あなたが直面している停滞期のタイプをしっかり見極めて適切な対処法で乗りこえましょう♪
ダイエット中の停滞期「5タイプ別の原因&解消法」
タイプ1.ダイエット初期の体重減少

ダイエットを始めるにあたって、まず食事の量を減らす人が多いかと思います。
がんばって食事の量を減らしていると、1~2キロは割と短期間で減少します。そしてこの「短期間で減った体重についての勘違い」が一つ目のタイプです。
いきなりですが、人間の体内の水分量というのは体重の60%を占めています。
例えば体重50キロの人の場合だと、水分量は約30キロです。これってかなりの量ですよね、そして食べものにも水分は多く含まれています。
- 摂取する食べものの量を減らす
- 体内の水分量&胃や腸に残る食べものの量が減る
- 短期間での体重の減少が起こる
こういった状況が生じます。しかし、正しい知識がないと以下のように勘違いしてしまいます。
- 初期の体重減少が起こる(水分や胃の内容物が減っただけ)
- 水分量が落ちつくことで体重が減らなくなる
タイプ1における停滞期の解消法
それでは解消法を見ていきましょう。
このタイプでは始めに説明した、「体内の水分量や食べもので1~2キロはすぐ変化する」ということをしっかり理解することが大切です。
ここで変化がないからとメニューを増やしたり、食事の量を減らしたりすると無理なプログラムになって挫折する原因につながってしまいます。
初期の早い体重減少と異なり、脂肪の燃焼による体重減少はもっと時間のかかるものです。
ダイエットをはじめてすぐの体重減少に惑わされずに、もう少し今のペースでダイエットを続けてみて下さい。
タイプ2.ダイエット中の生理周期

生理の前後ではかなり体重や体脂肪率に変化がおきます。
ホルモンバランスが原因となって、生理前には水分をため込みやすく体重が増えやすいんですね。
そのために女性の場合は特に、一ヶ月の中でも数値が荒れやすくなってしまいます。
このことは停滞期と勘違いしたり、逆にダイエットが順調だと思いこんだりする原因となります。
タイプ2の解消法
このタイプではどのように解決すればいいでしょうか。
こちらのタイプでも「生理前後での体重や体脂肪率の変化」に惑わされて、焦ってメニューを変更したり気を抜いたりしないよう注意が必要です。
また生理周期を頭に入れて、
とった感じで、なるべく同じ条件下で比べるようにしましょう♪
体脂肪率についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

タイプ3.省エネモードによる停滞期

私たちは普段あまり意識をせずに食事をします。
単純にお腹が減ったからご飯を食べますし、「最近では楽しみ・趣味」としての側面も強いかもしれません。
しかし本来食事の目的とは、体の機能を保つため・生きるのに必要なエネルギーを取り込むためです。
そのため急に入ってくるエネルギーが減ると、身体は燃料切れを恐れて消費カロリーを減らす省エネモードに入るといわれています。
これは「ホメオスタシス(恒常性)」と呼ばれる、体の状態を一定に保とうとする性質によるものです。
この省エネモードが停滞期の原因となるケースがタイプ3です。
タイプ3の解消法
急激に摂取カロリーを減らすほど体は危険を感じやすくなります。
そこでエネモードへの対策としては、なるべく緩やかに摂取カロリーを減らすことが大切です。
また省エネ状態は時間の経過と共に、エネルギー切れの心配がないと体が認識すれば解除されます。
このタイプに思い当たる人は摂取カロリーを緩やかにしつつ、少し様子を見てみましょう。
タイプ4.塩分の摂り過ぎによる停滞期

タイプ4は塩分による停滞期です。
塩分の摂りすぎは体重の減少を邪魔してしまいます。
塩分に含まれるナトリウムが体に多く入ると、ナトリウム濃度を薄めるために体が水分をたくさん引き込んでしまうからです。
このことが原因となって「カロリーの収支が適正でも体重が減りにくい」という現象を招いてしまいます。
という人はこのタイプかもしれません。
タイプ4の解消法
まず一度食生活を見直してみましょう。
塩分の摂りすぎに注意することで、停滞期を脱出できる可能性があります。
また、カリウムというミネラルにも注目です。
カリウムはナトリウムと体内でバランスをとっているので、カリウムが少なすぎてもむくみの原因になってしまいます。
ナトリウムと違って日常生活で不足しがちなため、塩分過多の人は意識して摂取したいところです。
- きゅうり
- わかめ
- タケノコ
- じゃがいも
- さつまいも
- 栗
この辺りはカリウムを多く含む身近な食品です。
注意点としてカリウムは水溶性なので、ゆで料理などでは栄養が抜けやすくなってしまいます。
調理する際は「煮汁も使う・水にさらし過ぎない」など工夫しましょう。
タイプ5.消費カロリーの低下による停滞期

以前と同じように運動や生活をしているつもりでも、無意識のうちに消費カロリーが減ってしまっているタイプです。
- 掃除の頻度が下がった
- 家で横になっている時間が多くなった
といったような日常の活動量の低下がないか見直しましょう。
「摂取カロリーを減らすことで動く量も自然と減ってしまっていた」というのは意外とよくあるケースです。
またその他にも、筋トレやジョギング・ウォーキングなど運動の消費カロリーが下がったパターンも考えられます。
<運動を始めたばかりのころ>
- 慣れていないフォーム
- ムダが多い
- 動きも多い
→ 結果として消費カロリーも多くなる
<運動が習慣づいたころ>
- 慣れてきて正しいフォームに
- ムダが少ない
- 動きも少ない
→ 自然と消費カロリーは減る
タイプ5の解消法
という人は意識して消費カロリーを増やす必要があります。
「運動の量をガッツリ増やす!」というよりも、まずは日常での活動量を増やす工夫をしてみましょう。
こちらの記事がおすすめです。

また、運動に慣れてきた人はメニューを一度見直してみるのも良いでしょう。
ムダが削られた事によって自然と省エネなフォームに進化した可能性があるので、トレーニングメニューをその分少しだけ増やすのも有りです。
ただしあくまで「少しずつ」増やすように。無理がないよう気をつけてくださいね。
「ダイエットが停滞期に入ってるのか」という判断

ダイエットが順調なのか、停滞しているのかは、複数の指標で判断するようにしましょう。
- 体重
- 体脂肪
- 腹囲
- 気になっている部分のサイズ(二の腕・太ももなど)
色々な数値を比べることでより正確な判断がしやすくなります。
そしてなるべく同じ条件下で比較することも大切です。
- 時間帯
- 食前・食後
- 入浴の前か後か
- 運動前・運動後
- 生理周期
- トイレの前・後
条件を揃えるほど正しい進行状況がわかるはずです。
そうすれば停滞期をひき起こしている原因もつきとめやすくなりますよ。
まとめ

停滞期といっても、その原因は一つではありません。
まずはあなたがどのタイプの停滞期に当てはまるのかを、客観的に見てしっかり判断しましょう。
そのうえでタイプに合わせて、
- 食事内容を見直す
- 日常の活動量をふやす
- トレーニングをふやす
- もう少し経過を見る
という4つの中から対策をとることができます。
ただし焦って食事を減らしたりトレーニングを増やしたりすることは、ダイエットを挫折してしまう原因になりやすいです。
もしメニューを変える場合でも「無理のないように、少しずつ・経過を見ながら」ということは忘れないでくださいね♪